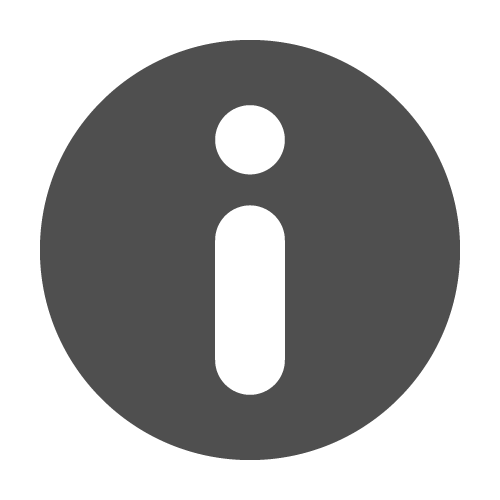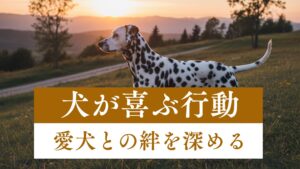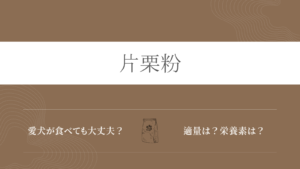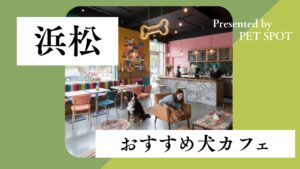「猫と仲良くできない犬種って本当にいるの?」「多頭飼いしたいけど、相性が心配…」
そんな疑問や不安を抱える飼い主さんへ。
犬と猫が仲良く安全に暮らすためには、犬種ごとの本能や性格の違いを知ることがとても大切です。
この記事では、猫との同居が難しいとされる“NG犬種”の特徴や代表例、逆に相性抜群の犬種の条件、さらに安全な同居スタートのためのポイントまで徹底的に解説!
初めての多頭飼いでも安心してトライできる知識を、たっぷり詰め込みました。
猫との同居が難しい!「NG犬種」に見られる共通の特徴
猫との多頭飼いを考えたとき、実はすべての犬種が猫と上手くやっていけるわけではありません。
ここでは「猫と仲良くできない犬種」に共通する本質的な特徴を、理由や具体例も交えて分かりやすく紹介します。
犬の本能や性格、生活環境によっては、想定外のトラブルや大きな怪我につながることもあるため、事前の知識が不可欠です。
特徴1:狩猟本能(プレデター・ドライブ)が極めて強い犬種
まず要注意なのが、強い狩猟本能を持つ犬種です。
犬の中には、動く小動物を見るとつい追いかけたり、捕まえたくなる本能が根強く残っている子もいます。
この本能は「プレイ・ドライブ」や「プレデター・ドライブ」と呼ばれ、テリア系やハウンド系(視覚・嗅覚で狩りをしていた犬)に特に顕著です。
たとえばジャック・ラッセル・テリアやヨークシャー・テリアは、小動物を捕まえるために生まれた歴史があり、家の中で猫を見ると反射的に追いかけてしまうことがあります。
また、ボルゾイやウィペットなどの視覚ハウンドも、素早く動くものに敏感に反応し、急な衝動で猫を追い詰めてしまうことも。
こうした犬種は、十分なトレーニングや慣らしを行わない限り、猫と安心して同居させるのは非常にハードルが高いと言えるでしょう。
要注意犬種リスト:テリア系(ジャック・ラッセル、ヨーキーなど)、視覚ハウンド系(ボルゾイ、ウィペットなど)
テリア系はもともとネズミや小動物を捕獲するために生まれた犬種で、遊びや本気の区別なく“獲物”を見つけるとスイッチが入ってしまう子が多いです。
またボルゾイやウィペット、サルーキといった視覚ハウンド系は、遠くの獲物を素早く察知し、一直線に追いかける能力を持っています。
このため、猫が家の中で急に走り出したときなど、思わぬ事故や怪我につながるリスクが非常に高くなります。
特徴2:警戒心が非常に強く、動きに敏感に反応する犬種
警戒心が強く、ちょっとした物音や動きにも反応しやすい犬種も、猫との同居には不向きなことが多いです。
特に日本犬(柴犬や甲斐犬、秋田犬など)は、元来“縄張り意識”が強く、知らない動物や素早い動きに敏感です。
見知らぬ猫が家の中にいるだけで警戒モードに入り、思わぬ攻撃性や追いかけ行動を見せることがあります。
また、一部の牧羊犬(コーギーやシェットランド・シープドッグなど)も、本来の仕事柄“動くものを追いかけてコントロールする”本能が強い場合があり、猫にストレスを与えることも。
犬自身にとっても強いストレスとなりやすく、無理に同居させるとトラブルが絶えない原因になります。
要注意犬種リスト:日本犬(柴犬など)、一部の牧羊犬
たとえば柴犬は、警戒心の強さに加えて小型動物への捕食行動も見られがち。
初対面の猫に対してもなかなか心を開かず、気の強い個体同士だとお互いにストレスが溜まりやすいです。
牧羊犬タイプでは、運動能力が高く、遊びの延長で猫を追いかける行動がクセになってしまうケースもあるので要注意です。
特徴3:興奮しやすい、または声が大きい犬種
興奮しやすく、よく吠える犬種は、静かな環境を好む猫にとっては大きなストレス源となります。
ポメラニアンやミニチュア・シュナウザーなど、警戒心や攻撃性、また吠え声の大きさが際立つ犬種は、猫が安心して暮らすことが難しくなる傾向があります。
また、個体によっては小型でも自分より小さい猫に対して“リーダー意識”を持ち、追いかけたり威嚇することもあるので注意が必要です。
こうした犬種の場合、同居を希望するなら子犬期からの徹底的な社会化やトレーニングが不可欠です。
猫と相性抜群!同居が成功しやすい「理想の犬種」の条件
猫と犬がストレスなく同居するには、やはり「犬種選び」や「性格の傾向」が大きなポイントになります。
ここでは猫との同居が成功しやすい犬の特徴や、安心して多頭飼いができるおすすめ犬種を具体的に紹介します。
大切なのは“相手を受け入れるおおらかさ”と“穏やかな生活リズム”を持った子を選ぶことです。
条件1:社会化期に様々な経験を積んでいること
社会化期(生後1〜3ヶ月)にたくさんの刺激や動物、人と触れ合ってきた犬は、他の動物に対しても柔軟に対応できる傾向があります。
子犬の頃から猫と一緒に暮らしていれば、「猫は家族」「安心できる仲間」と認識しやすく、成犬同士よりもスムーズに新しい関係を築けます。
成犬からの同居でも、社会化された犬であれば、飼い主のサポート次第で仲良くなるチャンスは十分あります。
新しい体験を前向きに受け止められる性格かどうかを見極めることが大切です。
条件2:飼い主への依存度が低く、穏やかな性格であること
おおらかで落ち着いた性格の犬種は、猫との同居にも向いています。
普段から自立心が強かったり、他の動物や家族にもフレンドリーなタイプなら、猫の行動にイライラせず、むしろ一緒にリラックスして過ごすことができます。
一方、常に飼い主だけにべったりな犬や、ちょっとした変化に敏感な犬種は、猫の存在をストレスに感じやすいので、慎重な見極めが必要です。
条件3:もともと攻撃性や闘争心が低い歴史を持つ犬種であること
犬種のルーツにも注目!もともと温厚で争いを避ける気質を持つ犬種は、猫との暮らしにも適応しやすいです。
たとえば人懐っこく友好的な家庭犬や、ペットとして改良されてきた犬種は、他の動物とのトラブルが起きにくい傾向。
攻撃性が低い犬種は、たとえ猫にちょっかいをかけられても「まぁいっか」と流せる寛容さを持っていることが多いです。
【小型犬】猫との同居におすすめの穏やか犬種3選
小型犬の中で猫と相性が良いとされるおすすめ犬種は、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、パグ、マルチーズです。
キャバリアは人や動物が大好きで、優しい性格が持ち味。
パグも明るく愛情深いので、猫にも優しく接することができるでしょう。
マルチーズは落ち着きがあり、穏やかな環境を好むので、猫との共生も比較的成功しやすい犬種です。
いずれも子犬期から社会化を進めれば、家族みんなで安心して暮らすことができます。
おすすめ犬種例:キャバリア、パグ、マルチーズ
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは、陽気で社交的な性格。
パグは遊び好きで愛嬌があり、他の動物にも寛容です。
マルチーズは警戒心が強すぎず、無駄吠えも比較的少ないため、猫のペースにも合わせやすい犬種として人気があります。
【中・大型犬】猫との同居におすすめの大人しい犬種3選
体格が大きい犬でも、性格が穏やかな犬種は猫との多頭飼いに向いています。
たとえばゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーは、愛情深く温和で家庭犬の代表格。
グレート・ピレニーズも優しい性格で、家族や他の動物を守る本能が強く、猫にもおおらかに接することができます。
もちろん、大型犬の場合は体格差による事故予防のために配慮やしつけが必要ですが、落ち着いた性格の子を選べば、猫との共生も十分に可能です。
おすすめ犬種例:ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー、グレート・ピレニーズ
ゴールデン・レトリバーはフレンドリーで他の動物との調和を大切にします。
ラブラドール・レトリバーも社交的で順応性が高く、多頭飼いの家庭にぴったり。
グレート・ピレニーズは包容力があり、おっとりとした性格なので、猫とも平和に暮らしやすい犬種です。
【同居前の準備】相性の良し悪しに関わらず徹底すべきルール
猫と犬の同居は「犬種選び」だけでなく、事前準備と環境づくりが成否を大きく左右します。
お互いが安心して暮らすためには、相性の良し悪しに関係なく守るべきルールや工夫がたくさんあります。
ここでは必ず押さえておきたい同居スタート前のポイントを、具体的に分かりやすく解説します。
ルール1:猫の「安全地帯(縦の空間)」を確保
猫は自分だけの“逃げ場所”や“休憩場所”をとても大切にします。
犬が絶対に入れないキャットタワーや高所、家具の上など、縦の空間をしっかり用意しましょう。
猫が「ここに逃げれば大丈夫!」と感じられる場所があれば、ストレスや不安を大きく減らすことができます。
この空間は犬から物理的に守られていることが大切なので、ドアやゲート、柵などを活用し、犬が侵入できない工夫をしてください。
特にシニア猫や体調が悪い猫には、より静かで落ち着けるスペースを確保することが必要です。
犬が絶対に入れない場所、猫が落ち着ける高所の設置
キャットウォークやキャットタワー、棚の上など、犬が絶対に届かない・登れない高い場所を家の複数箇所に設けるのが理想的です。
また、猫用の個室やケージを用意するのも有効な対策。
犬と猫が一緒に過ごす時間を増やす前に、まずは「逃げ場のある環境」を徹底しましょう。
ルール2:食事とトイレの完全分離
犬と猫の食事・トイレ場所は、必ず完全に分けることが鉄則です。
犬が猫のごはんやトイレを荒らしてしまったり、逆に猫が犬の食事を横取りしてしまうと、ストレスや健康トラブルにつながります。
食事スペースは、なるべくお互いの姿が見えない場所に設置しましょう。
また、猫のトイレは犬が侵入できない場所や、静かな部屋の隅などが最適です。
お互いのプライバシーを守ることで、安心して生活できる環境が整います。
お互いの食事を狙わせないための対策
食事の時間はタイミングをずらす、ドアやゲートを活用してエリア分けするなど、犬猫双方にとって安心できるルールを徹底しましょう。
猫がごはんを食べている間は犬を別室に移動させるなど、毎日の工夫が長期的なストレス防止につながります。
ルール3:犬の「落ち着き」を引き出すしつけの徹底
犬には「フセ」「待て」「おいで」などの基本トレーニングが必須です。
猫が近くにいても、飼い主の声や指示で落ち着いて待てる犬であれば、トラブルや事故のリスクをぐっと減らせます。
普段からおもちゃや遊びで興奮しやすい犬種は、猫と会う前から「落ち着く練習」を繰り返し行いましょう。
しつけが不十分なまま同居を始めると、犬が追いかけたり飛びかかったりする原因に。
まずは飼い主の指示で犬が興奮をコントロールできる状態を作ることが、猫との多頭飼い成功のコツです。
「フセ」「待て」などの指示で興奮をコントロールする練習
犬が「待て」や「フセ」の指示でしっかり落ち着いていられるようになれば、猫と顔を合わせるときも安心です。
猫が近づいてきた時やおもちゃで遊んでいる最中も、飼い主が落ち着かせることでお互いの安全が守られます。
日々のしつけやトレーニングは、愛犬の自信と落ち着きにもつながるので、ぜひ毎日の習慣にしてみてください。
犬と猫を「初対面」で失敗させないための段階的ステップ
いよいよ犬と猫を同居させるとき、一番大事なのは「最初の出会い方」です。
いきなり顔を合わせてしまうと、どちらかが怖がってパニックになったり、攻撃的になってしまうことも少なくありません。
焦らず段階を踏みながら慣らしていくことで、トラブルやストレスを最小限に抑え、安心して多頭飼いをスタートできます。
ここでは、安全かつ成功率が高い「犬と猫の初対面の流れ」を、わかりやすく3ステップに分けて解説します。
ステップ1:隔離期間中の「匂い交換」と「ポジティブ体験」
まずは犬と猫を完全に別の部屋で過ごさせることからスタートします。
お互いの姿を見せずに、まずはドア越しやケージ越しに「匂い」や「気配」に慣れてもらいましょう。
この期間には、お互いが使っているタオルやベッド、ブランケットなどを交換して、「相手の匂い=安心できるもの」と印象付けていくのが効果的です。
同時に、お互いの存在を感じながらご飯を食べたり、飼い主さんからたっぷり褒めてもらうことで、「相手がいる=良いことが起きる!」というポジティブなイメージを持ってもらいましょう。
この準備期間がしっかりできていれば、次の対面もスムーズに進む可能性が高まります。
ステップ2:安全な場所(ゲート越し、ケージ越し)での短時間対面
お互いの匂いに慣れてきたら、次は物理的な仕切りを使った“間接対面”です。
たとえばペットゲートや頑丈なケージ越しに、ごく短時間だけ顔を合わせてみましょう。
この時、犬は必ずリードをつけ、猫も逃げ場がしっかりある状態で安全を確保します。
最初は数分間だけにとどめ、両者が落ち着いていれば少しずつ時間を延ばしていきます。
お互いが緊張しすぎたり威嚇行動が強い場合は、すぐに距離を取り、最初のステップに戻して再挑戦。
短い時間と距離を守りつつ、褒め言葉やご褒美でポジティブ体験を強化するのがコツです。
ステップ3:犬にリードをつけた状態での対面と「ご褒美」
最後のステップは「犬にリードをつけたまま」飼い主がしっかりコントロールした上での直接対面です。
犬を落ち着かせてから猫に近づけ、猫が怖がっていないか常に様子を見ながらゆっくり進めます。
対面の最中はおやつや大好きなフードを使って「相手がいると嬉しいことがある!」と記憶づけるのがポイント。
猫が緊張したり犬が興奮し始めたら、すぐに距離を取って休憩を入れましょう。
無理に距離を縮めようとせず、必ず両者のペースを最優先にして。
もし喧嘩や興奮が見られた場合の「中断のサイン」
万が一、どちらかが強いストレスを感じたり、威嚇・攻撃行動が出たら即座に中断します。
無理に顔合わせを続けると、恐怖やトラウマにつながることもあるので、しばらく距離を置き、最初の段階からやり直すことが大切です。
また、飼い主が落ち着いて行動することで、犬猫ともに安心感を持ちやすくなります。
「慣れるまで何度でもゆっくり繰り返す」――これが成功への一番の近道です。
まとめ:犬種は目安!最終的には「個体差」と「飼い主の努力」が成功の鍵
猫と犬の多頭飼いを成功させるためには、犬種ごとの傾向や本能、性格を理解することが大切ですが、それだけにとらわれすぎない柔軟さも重要です。
確かに、狩猟本能や警戒心、興奮しやすさなど「猫と仲良くできない犬種」といわれる特徴は多く存在しますが、最終的に大切なのは「その子の個性」と「飼い主さんの丁寧な慣らし・工夫」に尽きます。
しっかりと社会化を行い、猫の安全地帯や食事・トイレの分離、基本トレーニングの徹底、そして「段階的な初対面」のルールを守れば、多くのケースで猫と犬が穏やかに暮らせるようになります。
もし途中でトラブルが起きても、慌てず、焦らず、「少しずつ」距離を縮めていく気持ちが大切。
多頭飼いは犬も猫も飼い主も、みんなが新しい発見や幸せを感じられる素敵なチャレンジです。
ぜひ今回のポイントを参考に、安全で楽しい“犬と猫の共生ライフ”を実現してください。