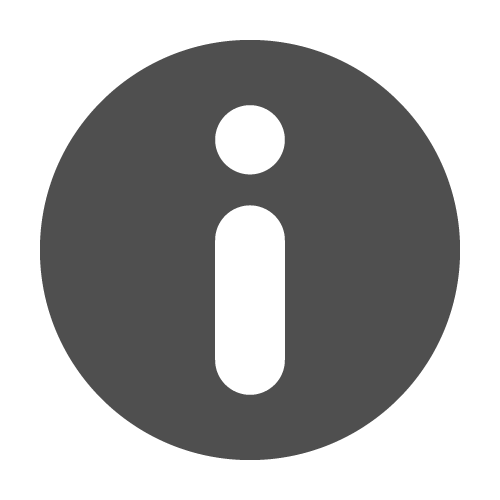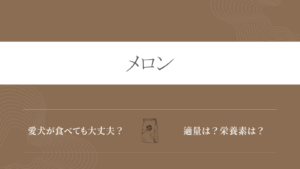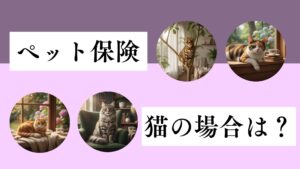季節ごとに美味しさを増すカツオ。
刺身やたたきなど、私たちの食卓でも定番の魚ですが、「香りに惹かれて愛犬がソワソワ…」「ちょっとだけ分けてあげたい」と思ったことがある飼い主さんも多いのではないでしょうか。
でも実は、犬に“生のカツオ”や“カツオのたたき”を与えるのはとても危険。
正しい知識で「安全なカツオの与え方」を守れば、トッピングやおやつとして健康サポートにも役立ちます。
今回は、犬にカツオを与える際の危険性と安全なポイント、そしておやつ・フード選びまで徹底解説します!
結論:中心まで加熱すれば少量ならOK!生やたたきは絶対NG
犬にカツオを与える場合は、必ず「中心までしっかり加熱」して骨や筋を取り除き、味付けせずにごく少量だけ与えてください。
刺身や、表面だけ炙った「カツオのたたき」は“生食”の扱いになり、寄生虫や中毒症状の危険があるため絶対NGです。
あくまでも主食のドッグフードを基本に、「ごほうび」や「トッピング」として少量だけを楽しみましょう。
与える前には愛犬の健康状態・体質・持病にも注意してください。
【最重要】犬に生のカツオやたたきが危険な4つの理由
なぜ加熱が絶対条件なのか?
カツオの刺身やたたきを犬に与えると、重大な健康リスクが潜んでいます。
ここでは、生やたたきがNGな4つの理由を徹底解説します。
①寄生虫「アニサキス」による食中毒
カツオをはじめとする海産魚には、「アニサキス」という寄生虫が潜んでいることがあります。
人間だけでなく、犬もアニサキスに感染すると激しい腹痛や嘔吐、食欲不振などの食中毒症状を引き起こします。
アニサキスは冷凍または70℃以上で加熱すれば死滅しますが、「たたき」や刺身のままではリスクが残ります。
②酵素「チアミナーゼ」によるビタミンB1欠乏症
生のカツオや魚介類には「チアミナーゼ」という酵素が含まれています。
この酵素はビタミンB1(チアミン)を分解・破壊してしまうため、続けて食べると「ふらつき・けいれん・神経症状」などの欠乏症を起こすリスクも。
加熱調理でチアミナーゼは失活するので、必ず火を通して与えることが必須です。
③「ヒスタミン」によるアレルギー様中毒
カツオのような赤身魚は、鮮度が落ちると「ヒスタミン」という物質が増えます。
これを犬が摂取すると「嘔吐・下痢・じんましん・かゆみ」などアレルギーに似た中毒症状を起こすことも。
ヒスタミン中毒は加熱しても完全には防げないため、「必ず新鮮なカツオを選ぶ」こともポイントです。
④黄色脂肪症(イエローファット)のリスク
カツオをはじめ青魚に多い「不飽和脂肪酸」を食べ過ぎると、「黄色脂肪症(イエローファット)」という病気を招くことがあります。
体内の脂肪が酸化して炎症を起こし、「お腹のしこり・発熱・痛み・食欲不振」などの症状が現れます。
青魚好きの猫に多い病気ですが、犬も与えすぎればリスクがあるため、必ず「ごく少量・おやつやトッピングだけ」を徹底しましょう。
加熱したカツオのメリット|DHA・EPAが豊富
「危険ばかりじゃなく、加熱したカツオにはどんな良いことがあるの?」
実はカツオは、しっかり加熱し安全に与えれば、愛犬の健康サポートにも役立つ栄養豊富な魚です。
ここでは、犬にとってうれしい加熱カツオの栄養メリットを分かりやすくご紹介します。
DHA・EPA(オメガ3脂肪酸):皮膚や被毛、関節、心臓、脳などの健康維持をサポート
カツオには「DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)」がバランス良く含まれています。
DHAは脳や神経の発達・認知機能維持、EPAは血液をサラサラに保ち、心臓や関節の健康維持にプラス。
オメガ3脂肪酸は体の中で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。
皮膚や被毛の艶、アレルギーや炎症のケア、子犬の脳の発達サポートにもおすすめです。
良質なタンパク質:筋肉や体の組織を作るのに欠かせません
カツオは100gあたり約25.8gものタンパク質を含む高タンパク食材。
犬の筋肉・内臓・皮膚・被毛など体の構造の材料となる必須の栄養素です。
しかも、脂質は比較的低めでカロリーも抑えめ。ダイエット中の犬やシニア犬にもトッピングで少量なら◎。
高品質なタンパク源を加えることで、運動好きな犬や成長期のサポートにも役立ちます。
鉄分・ビタミンB群:貧血予防やエネルギー産生に役立ちます
カツオには「鉄分」「ビタミンB12」「ビタミンB群」なども豊富に含まれています。
鉄分は赤血球や筋肉の材料となり、貧血予防や元気な体づくりに欠かせません。
ビタミンB群は代謝・エネルギー産生をサポートし、疲労回復や被毛の健康にもプラス。
特にビタミンB12は犬の体内で合成できないため、魚や肉から摂るのが理想です。
犬への安全な与え方と調理法
「愛犬にもカツオを安全に食べさせたい!」という場合は、必ず下処理と調理法にこだわりましょう。
間違った与え方をすると、食中毒やケガのリスクが高まるため注意が必要です。
以下では、犬にカツオを与える時の“絶対ルール”を詳しくご紹介します。
【必須】中心部までしっかり加熱する(茹でる・焼く)
カツオは必ず70℃以上で中までしっかり加熱しましょう。
おすすめは「茹でる」「焼く」「蒸す」など、油を使わずに調理する方法。
刺身や表面だけを炙った「たたき」は、生の部分が残るため絶対NGです。
加熱することで寄生虫・チアミナーゼなども安全になります。
与える前には手でほぐし、中まで火が通っているか確認してください。
骨や硬い筋は完全に取り除く
カツオには細かい骨や硬い筋が残りやすいので、必ず丁寧に取り除いてから与えましょう。
骨が残っていると喉や消化管を傷つけたり、腸閉塞の危険が高まります。
特に小型犬・シニア犬・子犬には細かくほぐし、食べやすい大きさにカットしてからあげてください。
味付けは一切しない(たたきのタレや薬味はNG)
人間用のカツオのたたきに添えられるポン酢・しょうゆ・塩・薬味(ネギ、ニンニク等)は絶対にNG。
これらは犬にとって中毒や塩分過多、胃腸障害のリスクになります。
必ず味付けなし・薬味なしで素材そのままを少量与えてください。
アレルギーがないかごく少量から試す
初めてカツオを与える時は、ごく少量(1かけら程度)からスタートし、食後24時間は体調や皮膚の変化、便の様子をよく観察しましょう。
嘔吐・下痢・かゆみ・発疹・元気がなくなるなど異常があればすぐ中止し、必要に応じて動物病院へ相談を。
【量に注意】犬に与えても良いカツオの適量は?
カツオは栄養豊富でおいしいごちそうですが、与えすぎるとカロリーオーバーや脂肪酸の摂りすぎ、健康リスクにつながります。
ここでは「安全に楽しむための1日あたりの適量」を犬の大きさ別に詳しく解説します。
カツオはあくまで“主食”ではなく、おやつ・トッピングの範囲で与えるのが原則です。
1日あたりの目安量
加熱したカツオを与える場合の目安量は、1日の摂取カロリーの10%以内が安全ラインです。
下記はお刺身に換算した目安となりますが、愛犬の体格・運動量・健康状態によって調整しましょう。
| 犬の大きさ | 1日あたりの目安量 |
|---|---|
| 小型犬(~10kg) | 15g(刺身1切れ弱) |
| 中型犬(~25kg) | 30g(刺身2切れ) |
| 大型犬(25kg~) | 50g(刺身3~4切れ) |
いずれも毎日与えるのではなく、“時々のごほうび”や食欲が落ちた時の「ちょい足し」感覚で使いましょう。
肥満傾向の犬や、腎臓・心臓病などの持病がある場合は、必ず獣医師に相談してください。
市販の犬用カツオおやつと与える際の注意点
最近は犬用に開発されたカツオのおやつやトッピングもたくさん販売されています。
「手軽に使えて便利」「栄養補給やごほうびに使いたい」という方も多いはず。
ただし、市販品であっても与え方次第で健康リスクがあるため、必ず下記のポイントを守って使いましょう。
カツオ節、ジャーキー、ふりかけなど様々な種類がある
犬用カツオおやつには、カツオ節・ふりかけ・ジャーキー・ウェットフードタイプなど色々な種類があります。
犬用に塩分や添加物が調整されているものがほとんどですが、与えすぎはNG。
とくにカツオ節やふりかけは、粒が大きい場合は喉に張り付きやすいので、小型犬は細かくちぎってから使うと安心です。
与えすぎは黄色脂肪症のリスクに
どんなに安全なおやつでも、与えすぎると「黄色脂肪症(イエローファット)」やカロリーオーバーのリスクがあります。
パッケージ記載の給与量・推奨量を必ず守りましょう。
特に市販ジャーキーやドライタイプは、脂肪や添加物が多めの商品もあるので、体調や便の様子を見て「時々のごほうび」にとどめてください。
アレルギーや持病のある犬は慎重に
カツオアレルギーや、腎臓病・心臓病・アレルギー体質の犬は、市販おやつの中身にも十分な注意が必要です。
新しい商品を与える際は、ごく少量から始め、体調や皮膚・便の変化をしっかり観察しましょう。
持病がある場合や不安がある時は、必ずかかりつけ獣医師に相談してください。

まとめ
今回は「犬にカツオを与えても大丈夫?」というテーマで、加熱の必要性から生やたたきのリスク、適量や与え方・市販おやつの注意点まで詳しく解説しました。
カツオは、中心までしっかり加熱し、骨や筋・味付け・薬味を避ければ、ごく少量なら犬も安心して楽しめる魚です。
DHA・EPAや良質なタンパク質など健康メリットもたくさんありますが、生やたたき、過剰摂取は絶対にNG。
初めて与える時はごく少量から、体調やアレルギー反応を観察しながら使ってください。
市販の犬用おやつも“適量を守って時々だけ”、肥満や持病がある犬は必ず獣医師と相談の上で与えましょう。
毎日の主食はあくまで総合栄養食が基本。
カツオは愛犬の健康を彩る「ちょい足しおかず・ごほうび」として、安全・楽しく活用してみてください!