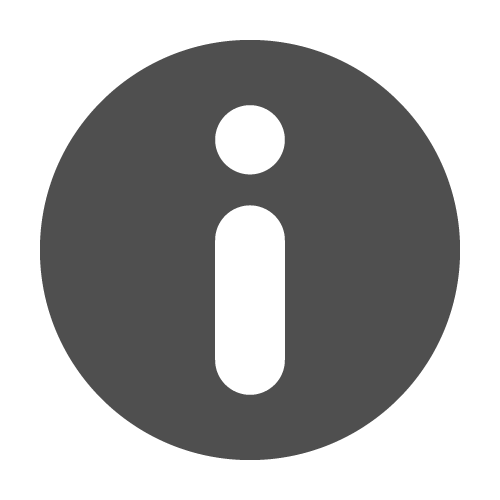結論:レバーは適量を守れば犬の健康に良い食材
栄養価が高いことで知られるレバーは、適切な量を守れば犬にとって素晴らしい健康サポート食材です。
レバーにはタンパク質・ビタミンA・鉄分・ビタミンB群など、体の基礎を作るうえで重要な栄養素がたっぷり詰まっています。
日々のフードにちょっと加えるだけで、貧血予防・免疫サポート・皮膚や毛並みの健康維持・疲労回復・スタミナアップなど、多彩な効果が期待できます。
一方で、「栄養がある=たくさん食べさせたい」と思いがちですが、与えすぎはかえってビタミンAの過剰摂取や肥満、消化不良などの健康リスクにつながります。
大切なのは、年齢や体格に合わせた目安量を守り、バランス良く活用することです。
しっかり加熱し、フードのトッピングやおやつとして少しずつ取り入れていきましょう。
犬にレバーを与えるメリット|豊富な栄養素とその効果
ここでは、レバーに含まれる代表的な栄養成分が犬の健康にどんなメリットをもたらすのかを解説します。
美味しくてスタミナ満点のレバー、そのパワーを存分に活かしてみませんか?
筋肉や体を作る「良質なタンパク質」
レバーは高タンパク・低脂肪で、筋肉・皮膚・内臓などあらゆる組織を作る材料となります。
タンパク質が不足すると、筋力低下や免疫力の低下、被毛のパサつきなど健康への影響が大きく、日々の食事でしっかり補給したい成分です。
レバー100gに含まれるタンパク質は約20g。これはささみや一般的な肉類と同等以上の含有量です。
特に成長期の子犬や、運動量が多いアクティブな犬には、レバーを加えることで筋肉や活力アップを効率的にサポートできます。
「食が細い犬」「高齢で筋肉が落ちやすい犬」にも頼りになる食材です。
目の健康をサポートする「ビタミンA」
レバーはビタミンAがとても豊富な食材。
ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持、視力のサポート、成長期の骨や歯の発達にも欠かせません。
ビタミンA不足は食欲不振や発育不良の原因になり、逆に不足を防ぐことで目の健康や免疫力アップ、皮膚トラブル予防にもつながります。
ただし、ビタミンAは「脂溶性ビタミン」で体内に蓄積されやすいため、与えすぎによる過剰症にも注意が必要です。
「週1~2回程度」「少量をコツコツ」が長く健康を保つ秘訣となります。
貧血予防に役立つ「鉄分」
血液をつくる材料になる鉄分は、特にレバーに豊富に含まれています。
その中でも吸収率が高い「ヘム鉄」は、体内で効率的に使われやすく、野菜や豆類の鉄分よりも効果的です。
貧血気味の犬、成長期や妊娠・授乳期、シニア期の犬にはとても心強いサポート役になります。
ビタミンCと一緒に摂ることで、さらに吸収率がアップするというメリットも。
レバーをトッピングやおやつで少しずつ取り入れて、毎日元気な赤血球づくりを応援しましょう。
元気の源になる「ビタミンB群」
ビタミンB群は、エネルギー代謝の「潤滑油」のような存在。
B1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンなど多くの種類があり、どれか一つが不足しても、元気に活動できません。
ビタミンB群は水溶性で体内にためておけず、尿と一緒に流れてしまうので、毎日まんべんなく摂ることが大切です。
レバーはこれらのビタミンB群を効率良く補える食材で、疲れやすい犬・元気がない犬・ストレスが多い犬にも効果的。
エネルギッシュな毎日を送りたい愛犬にぴったりの栄養サポートになります。
【最重要】レバーの与えすぎは危険!ビタミンA過剰症のリスク
どんなに健康に良いレバーも、与えすぎはかえって愛犬の健康を損なう原因となります。
特に気をつけたいのが、ビタミンAの過剰摂取です。
脂溶性ビタミンであるビタミンAは体内に蓄積されやすく、大量に取り続けると体に悪影響が出ることがあります。
そのため、「体にいいから」といって毎日たくさん食べさせたり、ドッグフードにプラスしてトッピングしすぎるのはNGです。
ここではビタミンA中毒のリスクや、どれくらいの量が危険なのかを詳しく解説します。
犬のビタミンA中毒とは?
ビタミンA中毒は、長期間にわたって過剰なビタミンAを摂取したときに起こります。
症状としては、骨や関節の変形、関節炎、皮膚の乾燥、被毛の異常脱毛、体重減少、消化不良などが現れることがあります。
特に子犬や成長期の犬は、骨の成長に悪影響が出やすく、重症になると日常生活にも支障が出てしまいます。
また、シニア犬や持病のある犬、もともとビタミンAを多く含むフードを食べている犬も、過剰症になりやすいので要注意です。
元気がない・動きがぎこちない・食欲が落ちる・皮膚がガサガサする…などの異変があれば、早めに動物病院で相談しましょう。
どのくらいで過剰摂取になる?
ビタミンAの過剰摂取の「安全ライン」は個体差が大きく、体重や食生活によっても異なります。
参考目安としては、小型犬で1日20gまで、中型犬で20~40g、大型犬で40g以上が一般的な適量とされています。
この量を大幅に超えて与えたり、毎日続けて大量に与えると、数週間~数か月でビタミンA過剰症になるリスクが高まります。
特にレバーを主原料とする手作りごはんの場合は、他の食材とのバランスやフードとの兼ね合いも考慮しましょう。
また、おやつやトッピングとして週1~2回までに抑えると、過剰症のリスクをグッと減らせます。
愛犬の健康のためにも、「少しずつ・間隔を空けて」を徹底してください。
犬に与えても良いレバーの適量(1日あたり)
レバーは栄養価が高いだけに、適量を守って与えることが最重要です。
ここでは体重別に目安となるレバーの1日あたりの上限量をご紹介しますので、愛犬のサイズや体質に合わせて、過剰にならないようにコントロールしましょう。
また、レバーはあくまでおやつやトッピングとして使い、主食のドッグフードとのバランスを考えて量を調整するのがコツです。
与える頻度の目安は週1~2回程度にとどめるのがおすすめです。
| 犬の大きさ | 1日あたりの目安量 |
|---|---|
| 超小型犬 | ~10g |
| 小型犬 | ~20g |
| 中型犬 | 20~40g |
| 大型犬 | 40g~ |
| 子犬・老犬 | 最初はごく少量から |
上記はあくまでも参考値です。
体調や運動量、日々の食事内容によって適量は変わりますので、最初は少量からスタートし、体調やうんちの状態を見ながら調整しましょう。
アレルギーや持病がある場合、投薬中の場合は必ず獣医師に相談してください。
また、レバーを使ったおやつ(ペーストやスープ)などの総量も、この表を目安に加算しましょう。
おやつやトッピングでレバーをあげた日は、その分ドライフードを少し減らすとバランスが保てます。
犬に安全なレバーの与え方|調理と下処理のポイント
レバーを犬に安心して与えるためには、調理や下処理の工夫がとても大切です。
生のままや鮮度の落ちたもの、下処理が不十分な状態は、食中毒や消化不良のリスクにつながることも。
ここでは安全に美味しくレバーを楽しんでもらうためのポイントを詳しく紹介します。
【必須】必ず加熱処理をする(食中毒・寄生虫予防)
レバーは必ずしっかりと加熱してから与えましょう。
生のレバーには、カンピロバクターやサルモネラなどの食中毒菌・寄生虫が含まれている可能性があります。
犬は人間よりも胃酸が強いものの、体調を崩しやすい子犬や高齢犬では特にリスクが高まります。
加熱の目安は「中心温度63℃で30分」または「75℃で1分間以上」。
茹でる・蒸す・焼くなど、愛犬の好みに合わせて調理しましょう。
加熱後は必ず冷ましてから小さく切って与えるのがベストです。
鮮度の良いレバーを選ぶ
レバーは鮮度が落ちやすい食材なので、人が食べるレベルの新鮮なものを選びましょう。
表面が白っぽく濁っていたり、独特の臭みが強い場合は鮮度が落ちているサインです。
購入後はできるだけ早く使い切り、余った分は小分けして冷凍保存しておくと便利です。
調理前・調理中・保存時も、衛生管理(手洗い・器具の使い分け)をしっかり徹底してください。
臭みを取るための下処理方法(血抜き)
レバー特有の臭みやアクが気になる場合は、血抜きや下処理をしてから加熱調理をしましょう。
流水でやさしく洗い、表面の血のかたまりや黄色い脂肪を取り除きます。
牛乳に10分ほど浸してから調理すると、さらに臭みが和らぎ、犬も食べやすくなります。
レバーとハツがくっついている場合は、キッチンバサミで筋を切り分けてください。
細かく切ることで火も通りやすく、食べやすいサイズになります。
主食ではなくトッピングやおやつとして活用する
レバーは栄養が濃いため、主食ではなくトッピングやおやつの位置づけで活用するのがベストです。
ドッグフードに混ぜたり、おやつとして与える程度にとどめることで、バランスの良い食生活が維持できます。
ドッグフードの10%を目安に加える場合は、必ずその分フードを減らしてカロリー過多を防ぎましょう。
また、香りや食感が良いので薬を包んで与えるときにも便利です。
レバー入りおやつは嗜好性も高いので、食が細い愛犬のご褒美や食欲増進にもおすすめです。
老犬(シニア犬)にレバーを与えても大丈夫?
年齢を重ねて食が細くなった老犬(シニア犬)にとって、レバーは栄養価が高く、嗜好性も抜群なサポート食材です。
しかし、シニア期は消化機能や内臓の働きが若い頃より低下している場合があるため、与え方や量にはより細かな配慮が必要です。
ここでは、老犬にレバーを与えるメリットや注意点を詳しく解説します。
老犬に与えるメリット
レバーは少量で高い栄養価が得られるため、食欲が落ちた老犬や、痩せやすい体質のシニア犬の強い味方となります。
タンパク質や鉄分、ビタミンB群などが補給できるので、体力維持や貧血予防、免疫サポートに役立ちます。
特にビタミンAは皮膚や粘膜、目の健康に関わるので、老化によるトラブルをサポートする栄養素です。
レバー特有の香りや味が、食欲低下時のご褒美や食事のアクセントにもなります。
どうしてもドライフードだけでは食が進まない場合、レバーのトッピングやペースト、スープ仕立てのおやつにしてみましょう。
与える際の注意点(消化への配慮、持病との関係)
一方で、レバーは消化にやや負担がかかる食材でもあります。
シニア犬や胃腸が弱い犬には、少量を細かく刻んで加熱調理し、消化を助ける工夫をしましょう。
また、腎臓や肝臓に持病がある犬、コレステロール値が気になる犬、アレルギー体質の犬には必ず獣医師と相談してから与えることが大切です。
最初はほんの少しずつ試し、体調の変化やうんちの状態をよく観察してください。
脂質やコレステロールも豊富なので、毎日ではなく週に1~2回、ほんの少量から始めるのが安心です。
愛犬の健康状態や体調によって、「与えない方が良い」場合もあることを覚えておきましょう。
犬のレバーに関するQ&A
レバーを犬に与えるとき、多くの飼い主さんが気になる「市販の缶詰製品」「豚・牛レバー」「アレルギー」などの疑問について、しっかりと解説します。
愛犬の健康を守るためにも、最新の知識を身につけておきましょう。
市販のレバー缶詰は与えても大丈夫?
犬用に作られたレバー缶詰であれば、基本的に与えても問題ありません。
ただし、人間用の缶詰は塩分や調味料、保存料が多く含まれていることがあるため、必ず「犬用」と明記されている商品を選ぶことが大切です。
また、パッケージの注意書きをよく確認し、1回の給与量や保存方法を守りましょう。
開封後は早めに使い切り、残りは冷蔵保存し、できれば数日以内に食べきるようにしてください。
犬用のレバー缶詰は毎日与えてもいい?
総合栄養食でない限り、レバー缶詰を毎日与えることはおすすめできません。
おやつやトッピング、特別なご褒美として週1~2回を目安に使いましょう。
毎日与えると、ビタミンAや脂質、カロリーの過剰摂取や栄養バランスの乱れにつながることがあります。
また、体調や体重の変化、うんちの様子もチェックし、何か気になる変化があれば一時的に控えるようにしましょう。
鶏レバー以外に豚や牛のレバーは?
鶏・豚・牛いずれのレバーも犬に与えてOKですが、初めての場合は必ず少量から試してください。
豚や牛のレバーは鶏レバーよりやや脂質やコレステロールが多く、消化に負担がかかることもあります。
特に豚レバーは臭みが強く、犬によっては好みが分かれる場合も。
鶏レバーは比較的クセが少なく、ペーストやおやつ、薬のトッピングにも使いやすいです。
いずれの場合も、必ず加熱調理し、最初はごく少量からスタートするのが安全です。
アレルギーの心配はない?
レバーや内臓系にアレルギーを持つ犬も一定数います。
初めて与える場合はごく少量を与え、皮膚の赤み・かゆみ・下痢・嘔吐などの異変が出ないかを必ず観察しましょう。
過去に食物アレルギーを経験したことがある犬、アトピー体質の犬、消化器系が弱い犬は特に注意が必要です。
万が一症状が現れた場合は、すぐに中止し、獣医師に相談してください。
また、投薬中や療法食を与えている場合も、必ず主治医と相談のうえで新しい食材をプラスしましょう。
【簡単レシピ】手作りレバーおやつの作り方
レバーは市販品だけでなく、ご家庭でも簡単に美味しい犬用おやつとして手作りできます。
ここでは基本のゆでレバーやパウダー(ふりかけ)など、毎日のごはんや特別なご褒美に活用できるアレンジ方法を分かりやすくご紹介します。
手作りなら保存料や添加物もなく、安心・安全に愛犬の食事をグレードアップできますよ。
鶏レバーのゆで方(基本の下処理)
まずは、レバーを愛犬に与えるうえで一番シンプルで応用しやすいゆでレバーの作り方です。
(1)血のかたまりや黄色い脂肪を取り除き、流水でやさしく洗う。
(2)適当な大きさにカットし、鍋にかぶる程度の水とともに入れて中までしっかり火を通す(目安:中心温度63℃で30分以上、または75℃で1分以上)。
(3)火が通ったらザルに上げ、冷めたら食べやすい大きさに切って完成。
アクを取ることで臭みも抑えられ、犬も食べやすくなります。
できあがったレバーは冷蔵で2日程度・冷凍なら1週間程度保存可能。
冷凍保存の場合は1回分ずつ小分けにしておくと便利です。
レバーのパウダー(ふりかけ)の作り方
食欲が落ちているときや、フードのトッピングとして便利なレバーのパウダー(ふりかけ)の作り方もご紹介します。
(1)上記の方法でゆでたレバーを、キッチンペーパーなどでしっかり水気を取る。
(2)細かく刻んでからフードプロセッサーやすり鉢などで粉砕し、さらにフライパンやオーブンで軽く水分を飛ばす。
(3)カリカリ・パラパラになったら完成。冷蔵庫で保存し、1週間を目安に使い切ってください。
市販のふりかけよりも無添加で安心、毎日のごはんにサッとかけるだけで、香りと栄養アップになります。
愛犬が喜ぶ簡単おやつアレンジ
ゆでレバーやレバーパウダーは、ヨーグルトと混ぜてペースト状にしたり、細かく刻んで手作りスープやミートボールに加えたりとアレンジ無限大。
食が細い子には、レバーの香りを生かして食欲UPメニューにもおすすめです。
与えるときは、必ず冷ましてから、目安量を守って与えること、冷蔵保存は2日以内、冷凍保存なら1週間以内で使い切りましょう。
愛犬の好みに合わせて色々な食べ方を楽しんでみてください。

まとめ
今回は犬にレバーを与える際のメリット・注意点・与え方のコツについて、徹底的に解説しました。
レバーはタンパク質やビタミン、鉄分などが豊富で、愛犬の元気や健康づくりに役立つパワーフードです。
ただし、与えすぎるとビタミンA過剰症や消化不良、肥満のリスクが高まるため、必ず体重に合った適量を守り、週に1~2回までのご褒美やトッピングにとどめるのが安心です。
また、必ず加熱し、鮮度や下処理・調理法にも気を配ることが、安全なごはん作りのポイント。
老犬や子犬、アレルギー・持病のある犬に与える場合は特に注意し、最初は少量から始めて、体調や便の状態をしっかり観察しましょう。
レバー缶詰やレバーパウダーなど市販品を使うときも、成分表やパッケージをよく確認し、「犬用」と明記されたものを選ぶことが大切です。
ご家庭で手作りする場合も、無理なく保存・活用できる範囲で楽しんでください。
正しい知識とほんの少しの工夫で、レバーは愛犬の健康をグッと底上げする素晴らしい味方になります。
毎日の食事がもっと楽しく、ワクワクしたものになりますように──飼い主さんと愛犬の健やかな日々を応援しています!