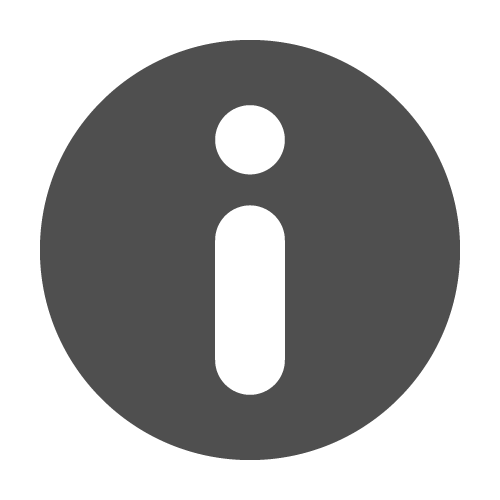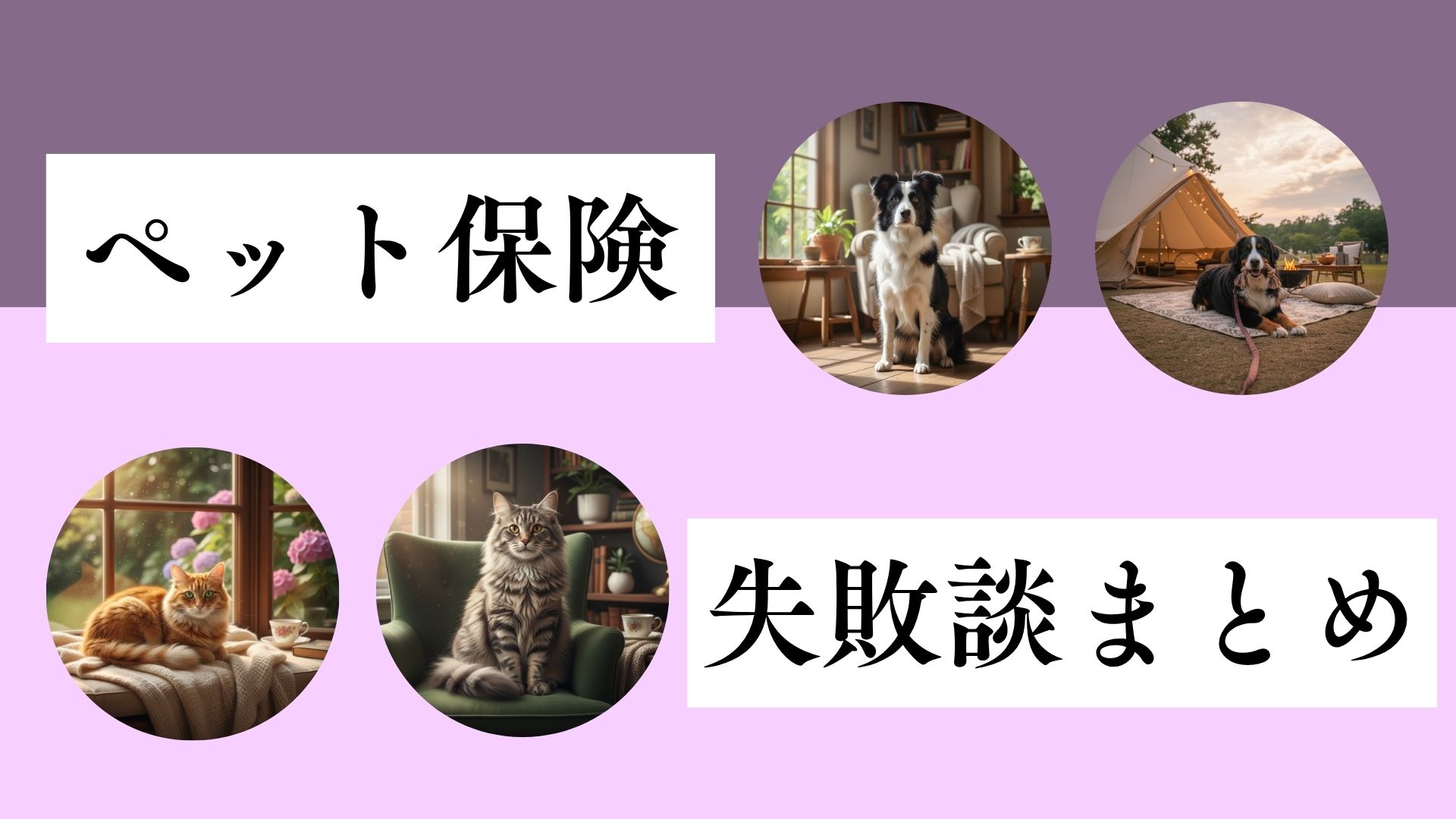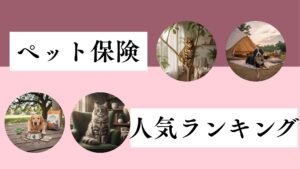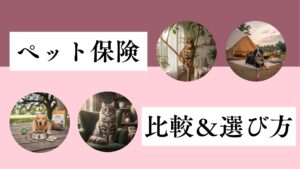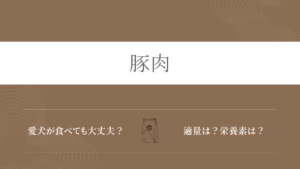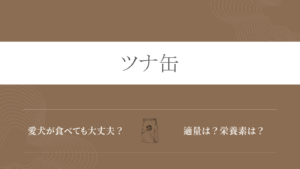「ペット保険って本当に必要?」「正直いらないのでは?」
そんな迷いや疑問を感じている飼い主さんへ。
今回は、ペット保険の“いらない”という声と“必要”な人の違いを徹底検証し、やめた理由・解約者の本音・失敗しない選び方まで
参考データをたっぷり交えながら超ていねいに解説します。
最後まで読むと「自分に本当に必要か?」がクリアになる内容です。
はじめに:なぜ今、ペット保険の必要性が問われているのか?
近年、ペットの高齢化や医療技術の進化とともに、治療費は年々高額化。
ペット保険の契約数も増加していますが、「いらない」「もったいない」という声も根強いのが実情です。
公的医療保険のない犬や猫の医療費は全額自己負担。
「何十万円も突然の出費が…」という事態に備えたい反面、「保険料がムダだった」「全然使わなかった」と感じるケースも。
ペット保険は“安心”を買うものですが、人によって本当に必要かどうかは変わります。
この記事では両面からリアルな実態と判断軸をお伝えします。
【徹底検証】ペット保険は「いらない」?不要論者の3つの主な理由
「ペット保険はいらない」「途中でやめた」「掛け捨てでムダ」といった声が多いのはなぜなのでしょうか?
ここでは実際の解約者やネットの口コミから見えてくる「ペット保険が不要だと考える主な理由」を徹底分析します。
どんなポイントが“不満”や“後悔”に繋がるのか、その背景をわかりやすく解説します。
「途中でやめた理由」から見る!解約者が不満に感じた点(猫の事例含む)
ペット保険を「やめた」「解約した」という人の理由は大きく3つに集約されます。
1つ目は保険料の家計負担や値上がり。
ペットが若い頃は保険料も安いですが、シニア期(7歳~9歳以降)になると急激に保険料が高くなり「払えなくなった」という声が多く見られます。
2つ目は補償対象外の治療や免責金額が多いこと。
例えば、パテラ(膝蓋骨脱臼)や外耳炎など補償対象外の病気があり「いざという時に保険が使えなかった」、また免責金額設定で「少額の治療費は全部自己負担」など、思っていたより使い勝手が悪いと感じたケースです。
3つ目は保険金請求の手間や利用頻度の少なさ。
「ほとんど病気しなかった」「請求が面倒」「結局使わず払い損」という不満があがっています。
これらの声は、特に健康な猫や若い犬の飼い主から多く聞かれます。
- 保険料が家計の負担になった、または値上がり幅が大きい
- 補償対象外の治療や免責金額が多く、利用メリットを感じなかった
- 保険金を請求する頻度が低く、「もったいない」と感じた
ズバリ!ペット保険への加入が「不要な人」の特徴
ペット保険が本当に「いらない」といえるのは、どんな飼い主さんでしょうか?
不要論者の特徴をまとめると、十分な貯金がある・高額治療にこだわらない・リスク許容度が高いなどが挙げられます。
たとえば「数十万円の治療費でも動じない貯金がある」「もしもの時は治療を諦める覚悟がある」など、家計に大きな余裕がある人や、治療に対して割り切った考えを持つ方はペット保険が不要といえます。
また、ペットの高齢化で保険料がどんどん上がることに納得できない場合や、月々の固定費を極力減らしたい方にも保険は向いていません。
- ペットの医療費を全額貯金で賄える十分な資産がある
- 高額な治療を望まず、治療方針に強いこだわりがない
「ペット保険 いらない 知恵袋」などの疑問に答える!猫と犬の不要論の違い
「ペット保険は猫ならいらない?犬は必要?」といったネット上の質問も多く見られます。
たしかに、猫は犬に比べて病気やケガでの通院・手術回数が少ない傾向があり、保険料をムダに感じる人もいます。
しかし近年では、腎臓病や尿路結石など高額治療が必要になるケースも増加しているため、一概に「猫は不要」とは言い切れません。
犬の場合は、パテラやヘルニア、異物誤飲など、年齢や犬種によっては通院・手術のリスクが高く、保険の恩恵を感じやすい傾向です。
結論としては、「いらない」かどうかは飼い主の価値観・家計・ペットの健康状態次第。
後悔しないためには、加入前に本当に自分に合うかどうかじっくり検討することが大切です。
こんな人には必須!ペット保険の必要性が高い人の特徴とメリット
ここからは逆に「ペット保険に入るべき人」「保険の必要性が高い飼い主さん」の特徴と、具体的なメリットを解説します。
「うちは絶対に必要!」と感じるケースや、実際の保険金支払い事例まで、リアルな情報をたっぷり紹介します。
「万が一」に備えたい!ペット保険への加入が「必要な人」の特徴
ペット保険の加入を強くおすすめしたいのは、以下のような飼い主さんです。
急な高額出費が家計に響く、ペットの健康や治療方針に強いこだわりがある、高齢ペットを飼っている…そんな方には「もしもの時」の備えとして保険が心強い味方になります。
また、「ちょっとした異変でもすぐに動物病院に行きたい」「高額な治療や先進医療も受けさせたい」といった希望がある方も、自己負担を減らすことで気兼ねなく最善の選択ができます。
- 急な高額出費で生活費に影響が出ることに不安がある
- ペットの体調変化にすぐ対応し、常に最良の治療を受けさせたい
- 高齢ペットを飼っており、病気やケガのリスクが高い
実際の保険金支払い事例から見る自己負担額の軽減効果
実際にペット保険に加入して「助かった!」という体験談で最も多いのが、高額な手術や長期治療で自己負担が大幅に減ったという声です。
たとえば犬(トイプードル)の膝蓋骨脱臼(パテラ)では、治療費総額16万8,000円。
70%補償のプランなら約11万7,600円が保険金支払いとなり、自己負担額は5万円程度に。
猫(スコティッシュフォールド)が異物誤飲で手術となったケースでは、治療費22万円超がかかり、これも補償割合によって10万円以上カバーされる計算です。
こうした万単位の支払いが必要なとき、ペット保険があるかないかで安心感はまったく違います。
犬(例:トイプードル)の膝蓋骨脱臼(パテラ)治療費
トイプードルをはじめとする小型犬に多いパテラ(膝蓋骨脱臼)は、1回の治療費が10万円~20万円超えになることも。
内訳としては診察、検査、手術、麻酔、入院費などがかさみます。
70%補償なら「使った分だけしっかり戻る」ので、「入っていて良かった!」と実感する飼い主さんがとても多い疾患のひとつです。
猫(例:スコティッシュフォールド)の腎臓病治療費
猫の場合、腎臓病や泌尿器疾患で通院・入院・点滴などが長期間必要になりやすく、合計で数万円~十数万円単位の治療費が発生。
また、異物誤飲での手術や内視鏡検査でも一度に20万円以上かかることもあります。
保険があることで「ためらわず治療を選べた」「自己負担が減って最新治療も選択できた」と満足する声が増えています。
失敗しないための!後悔しないペット保険の選び方7つの視点
ペット保険は「なんとなく」「月額だけ」で決めると、あとで「思っていたのと違った…」と後悔する声が本当に多いジャンル。
ここからは絶対に押さえておきたい7つの選び方の視点を徹底解説します。
内容をひとつずつ理解すれば、自分とペットにピッタリの“失敗しない保険”が必ず見つかります!
【視点1】補償内容:通院・入院・手術、どこまでカバーするか?
補償内容は最重要ポイント!
商品によって「通院のみ」「入院・手術だけ」「すべてフルカバー」など幅があります。
日常的なケガや病気も不安な方は通院補償つき、高額医療だけ備えたいなら手術・入院特化型など、ライフスタイルに合わせて選ぶのが後悔しないコツ。
特に猫の場合は、泌尿器系・腎臓系など長期通院になる疾患も多いので、どこまで補償されるかを必ず事前にチェックしましょう。
特に猫に多い泌尿器系の病気が対象かチェック
猫は「尿路結石」「腎臓病」「膀胱炎」など泌尿器系のトラブルが多く発生します。
こうした疾患が補償対象か・日額や年間限度額が十分か、パンフレットや公式サイトで必ず確認しましょう。
「よくある病気ほど補償外だった」「細かい条件が多すぎて使いにくかった」などの後悔も多いので注意!
【視点2】補償割合と免責金額のバランス
ペット保険の補償割合は50%、70%、100%などさまざま。
高いほど自己負担が減りますが、保険料もUPします。
また、免責金額(自己負担金)が設定されている商品も多く、「少額治療は自己負担になる」ことも。
「どこまで自己負担にするか?」「コスパと安心感のバランスは?」補償割合と免責金額のバランスをよく比較しましょう。
【視点3】保険料の生涯総額と「年齢による値上がり幅」
月額だけでなく、長く続けた場合の総支払額を必ずシミュレーションしましょう。
ペット保険は高齢になるほど保険料が上がるものが多く、「7歳から急に高額に!」「10歳で倍になった」などの後悔も多発。
パンフレットや公式サイトで年齢ごとの保険料表を必ず確認し、「10歳・15歳になった時の月額」を想定しておくと安心です。
【視点4】加入可能年齢と終身継続の有無
「何歳まで新規加入OK?」「途中で継続できなくなる?」も重要な選択ポイント。
特に高齢になってから加入・継続できる保険は減ります。
「生後2か月から11歳11か月まで」など商品ごとに加入可能年齢は異なるため、将来を見据えて“終身継続できる保険”を選ぶと失敗しません。
【視点5】保険金請求のしやすさ(窓口精算・アプリ請求)
実際に使うとき「窓口で精算できるか」「アプリ・Webで請求できるか」など、手続きの簡単さも要チェック。
アニコム損保やアイペット損保は窓口精算がラク、SBIプリズム少短やau損保などはWeb・アプリ請求に対応。
「書類を揃えて郵送するのが手間」という不満を避けるためにも、利用シーンを想像して選びましょう。
【視点6】補償対象外となるケース(待機期間・既往症など)
ペット保険には補償されない治療や病気・ケガがあります。
たとえば「既往症」「生まれつきの病気」「ワクチン・健康診断」「去勢・避妊」「待機期間中の発症」などはほぼ対象外。
細かい補償対象外条件を必ずチェックし、「何がNGなのか」「加入後どれくらいで補償が始まるのか」をしっかり理解しておきましょう。
【視点7】特約(ペット賠償責任など)の有無
ペット賠償責任特約やセレモニー費用補償、24時間健康相談など、各社独自の特約・付帯サービスにも注目!
他人や他の動物へのケガ・物損、飼い主への安心サポートなど、「自分に必要なもの」がついているか比べると選びやすくなります。
人気のペット保険比較!おすすめ3社のプランと特徴
ここでは、2025年最新のデータや利用者の満足度を参考に、特に支持されているペット保険会社3社のプランや特徴を徹底比較!
補償内容・保険料・使い勝手・独自サービスなど、「結局どこがいいの?」という疑問に答える実用的な内容です。
アニコム損保(どうぶつ健保ふぁみりぃ):対応病院が多く、窓口精算が手軽
アニコム損保の「どうぶつ健保ふぁみりぃ」は、全国の提携動物病院の窓口で保険証を提示するだけで自己負担分のみを支払い、その場で精算が完了する便利さが最大の魅力。
通院・入院・手術を幅広くカバーし、補償割合も50%・70%から選択可能。
ペット賠償責任特約や多頭割引、健康相談サービスなどの付帯サービスも充実しており、「請求が簡単&安心サポート」重視の飼い主さんから特に支持されています。
SBIプリズム少額短期保険(プリズムペット):柔軟な補償プランと付帯サービス
SBIプリズム少短「プリズムペット」は、補償割合50%~100%・日額制限なし・多頭割引ありと、幅広いニーズに対応できる柔軟な設計が特徴。
また、24時間の獣医師健康相談や飼育費用補償、エキゾチックアニマルへの対応(小動物・鳥類・爬虫類もOK)など、独自の付帯サービスも豊富。
「ペットの種類が多い」「相談窓口を重視」「コスパと安心を両立したい」という方におすすめです。
au損保(ペットの保険):高額治療に備える安心プラン
au損保「ペットの保険」は、入院・手術に特化したシンプルな設計と、通院もカバーできるプランを用意し、毎月の保険料を抑えたい方から、しっかり備えたい方まで幅広く対応。
支払い限度額や支払い回数が無制限(年間限度額まで)という特徴もあり、「とにかく高額治療にしっかり備えたい」という飼い主さんに選ばれています。
多頭割引や24時間健康相談、通院治療費用補償特約などのオプションも充実。
比較表:主要3社の料金(犬・猫/0歳/70%補償)と特徴
| 保険会社 | 主なプラン | 補償割合 | 年間補償限度額 | 月額保険料(犬0歳/例) | 通院・入院・手術カバー | 窓口精算 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニコム損保 | どうぶつ健保ふぁみりぃ | 70% | 70万円 | 3,590円 | ○ | ○ | 提携病院で即精算、賠償特約・多頭割引 |
| SBIプリズム少短 | プリズムペット | 50~100% | 最大225万円 | 4,740円(100%補償例) | ○ | × | 多頭割引・健康相談・幅広い補償設計 |
| au損保 | ペットの保険 | 70% | 70万円 | 2,480円 | ○ | × | 入院・手術特化、限度日数/回数なし |
加入前に知っておきたい!ペット保険に関するデータと基本知識
ペット保険は「みんな入ってるの?」「本当に必要なの?」と迷う方も多いはず。
ここでは日本のペット保険加入率やリスクデータ、各保険会社の違いなど、加入前に知っておくべき基本情報をたっぷり解説します。
これを読めば、納得して比較検討できるはずです!
日本のペット保険加入率と増加傾向
日本国内でのペット保険加入率は、2024年時点で20.1%(出典:アニコム ホールディングス株式会社統合報告書2024)。
まだ少数派に見えますが、ここ数年でじわじわと増加傾向にあり、多くの飼い主が“もしも”に備えて保険を検討・加入し始めています。
ペットの長寿化・高齢化が進み、高額治療や慢性疾患リスクの上昇も背景のひとつです。
ペットが病気やケガをする確率(犬・猫別データ)
ペットはどのくらいの確率で病気やケガをするのでしょうか?
Team HOPEの「ペットの健康管理に関する実態調査(2020)」によると、7歳以上の高齢ペットの罹患経験は犬で80%、猫で60%というデータがあります。
また、犬の年間治療費平均は約13万円、猫は約9万円という調査もあり、入院や手術となると1回で20万円~30万円を超える事例も珍しくありません。
これらは決して「一部の特殊な例」ではなく、一般的なリスクとして把握しておくことが大切です。
損害保険会社・少額短期保険会社の違い
ペット保険には「損害保険会社」と「少額短期保険会社(少短)」という2つのタイプがあります。
損保系は大手中心で、アニコム損保・アイペット損保・au損保など。
金融庁の厳格な審査・監督を受け、安定性やサポート力が高いのが特徴です。
少額短期保険会社(例:SBIプリズム少短・FPC・リトルファミリー)は、小規模で独自性や柔軟な商品設計が魅力。
また、保険料がやや安めな傾向も。
どちらも一長一短なので、信頼性とコスパ・プラン内容でしっかり比較しましょう。
よくある質問(Q&A):ペット保険に関する素朴な疑問を徹底解説!
ここでは、ペット保険について実際によく寄せられる疑問や不安に徹底的にわかりやすく回答します。
「加入時の注意点は?」「多頭飼いの場合は?」「途中解約や切り替えのリスクは?」など、見落としがちなポイントも網羅!
これを読めば、はじめての保険選びでも安心して一歩を踏み出せます。
Q. ペット保険の「途中解約」はできる?返金やリスクは?
途中解約はいつでも可能ですが、保険会社によっては日割り返金がない場合もあるので、事前に約款を確認しましょう。
また、いったん解約すると「高齢や既往症で再加入できない」リスクもあるため、慎重な判断が必要です。
「保険料の見直し」「プラン変更」は、継続中であれば相談できる会社が多いので、まずはカスタマーサポートに問い合わせるのがおすすめです。
Q. 多頭飼いの場合、保険はどう選ぶ?割引やお得な制度は?
2頭・3頭以上を飼っている方は、多頭割引や家族割引が使える保険会社を選ぶと月額コストを抑えやすいです。
アニコム損保やSBIプリズム少短、au損保など、主要な会社は多頭割引に対応しており、「頭数が増えるほど割引率が高まる」ケースも。
ただし、「契約ごとに条件が異なる」「ペットごとに補償内容を変えたい」場合は、個別に契約内容を比較しながらベストなプランを見つけましょう。
Q. 持病や既往症がある場合でも入れるペット保険はある?
多くのペット保険では、既往症や現在治療中の病気は補償対象外となります。
しかし、「特定部位や過去の治療歴だけを補償外」とし、それ以外は加入できる柔軟な会社もあります。
少額短期保険会社は持病持ちペット向けのプランがある場合もあるため、事前に保険会社へ「告知事項」を相談し、条件付き加入や限定補償の内容をしっかり把握しましょう。
Q. ペット保険の「待機期間」ってなに?いつから補償される?
待機期間とは、保険契約成立から実際に補償が始まるまでの期間のこと。
一般的に、「ケガは即日」「病気は30日後から」など条件付きで設定されていることが多いです。
待機期間中に発症した病気やケガは補償対象外となるため、「加入前からの病気」「すぐ治療が必要になった場合」に保険が使えない可能性があります。
契約前に、必ず各社の待機期間や適用条件をチェックしましょう。
Q. 保険金請求時に「必要な書類」は?申請の流れは?
保険金請求には、診療明細書や領収書の原本、そして保険会社指定の請求書類が必要です。
アニコム損保のように「窓口精算」対応の場合はその場で手続き完了ですが、郵送・Web申請が必要な会社も多数あります。
「どこまでが補償対象か」「どう書類を揃えるか」不明点は、保険加入時や通院前にサポート窓口で確認しておくと安心です。
実際どうだった?ペット保険の「利用者のリアルな口コミ・体験談」まとめ
保険選びに迷ったときに一番気になるのが「実際に使ってどうだった?」というリアルな声。
ここでは、ペット保険の解約経験者・利用継続中の飼い主さん双方の体験談や満足・不満ポイントを多数紹介します。
口コミの傾向を知ることで、「自分にとって後悔しない保険選び」がより明確になります!
「入ってて本当に良かった!」という満足派の口コミ
「うちの子が突然大きな手術になった時、保険に入っていたおかげで迷わず最善の治療ができました!」
「老犬で慢性疾患が続いているけど、毎月の通院費もきちんとカバーされて助かってます」
「異物誤飲や骨折など、予期せぬトラブルで数十万円かかったけど保険金が大半戻って本当にありがたかった」
「高齢になった今こそ保険のありがたみを痛感しています!」という声が圧倒的多数。
特に、「医療費の心配がなくなった」「獣医さんの提案を断らず治療できた」など、家族の安心感・選択肢の広がりが大きな満足ポイントです。
「途中でやめた…」という不満・後悔の声
「若い頃は全然使わず、保険料がもったいなかった」
「ペットがシニア期に入って保険料が急上昇、家計に負担で解約しました」
「細かい条件や補償対象外が多くて、実際に必要な治療がカバーされず不満」
「請求が手間だった」「もっと早く内容を見直せばよかった」など、費用面・使い勝手・補償範囲への不満が多く見られます。
特に、「数年払い続けてほとんど使わなかった」という声が多いのは、健康な若いペットの飼い主さんに目立つ傾向です。
口コミ・体験談から見えてきた「保険選びで後悔しないコツ」
多くの口コミからわかるのは、「自分の家計とペットの体質・年齢に合った保険選び」が何より大事ということ。
「どこまで治療したいか?」「いくらまで自己負担できるか?」を家族で話し合い、見積もりやパンフレットを細かく比較して選ぶことが大切です。
また、「入るなら若いうちから」「高齢化するほど保険料が上がる」ことも踏まえ、長期的な視点での判断が失敗を防ぐポイントになります。
不安や疑問は、公式サポートや口コミサイトでしっかり情報収集してから加入しましょう。
まとめ:ペット保険が「必要かどうか」本当に納得する選択を!
ここまで、ペット保険の「いらない」派・「必要」派両方の意見とその根拠、やめた理由・利用者の口コミ・失敗しない選び方・各社比較まで、徹底的に詳しく解説してきました。
ペット保険は、家計や価値観、ペットの年齢・体質によって最適な答えが違います。
「何となく」で決めるのではなく、家族みんなで「うちの子に本当に必要か?」を話し合い、データや体験談・各社の特徴をしっかり比較して検討することが後悔しない最大のコツです。
安心を“買う”のか、“備える”のか――あなたとペットの幸せな毎日のために、納得いく選択をしてください!