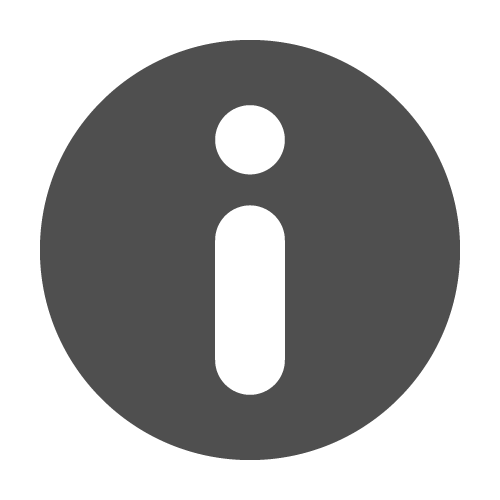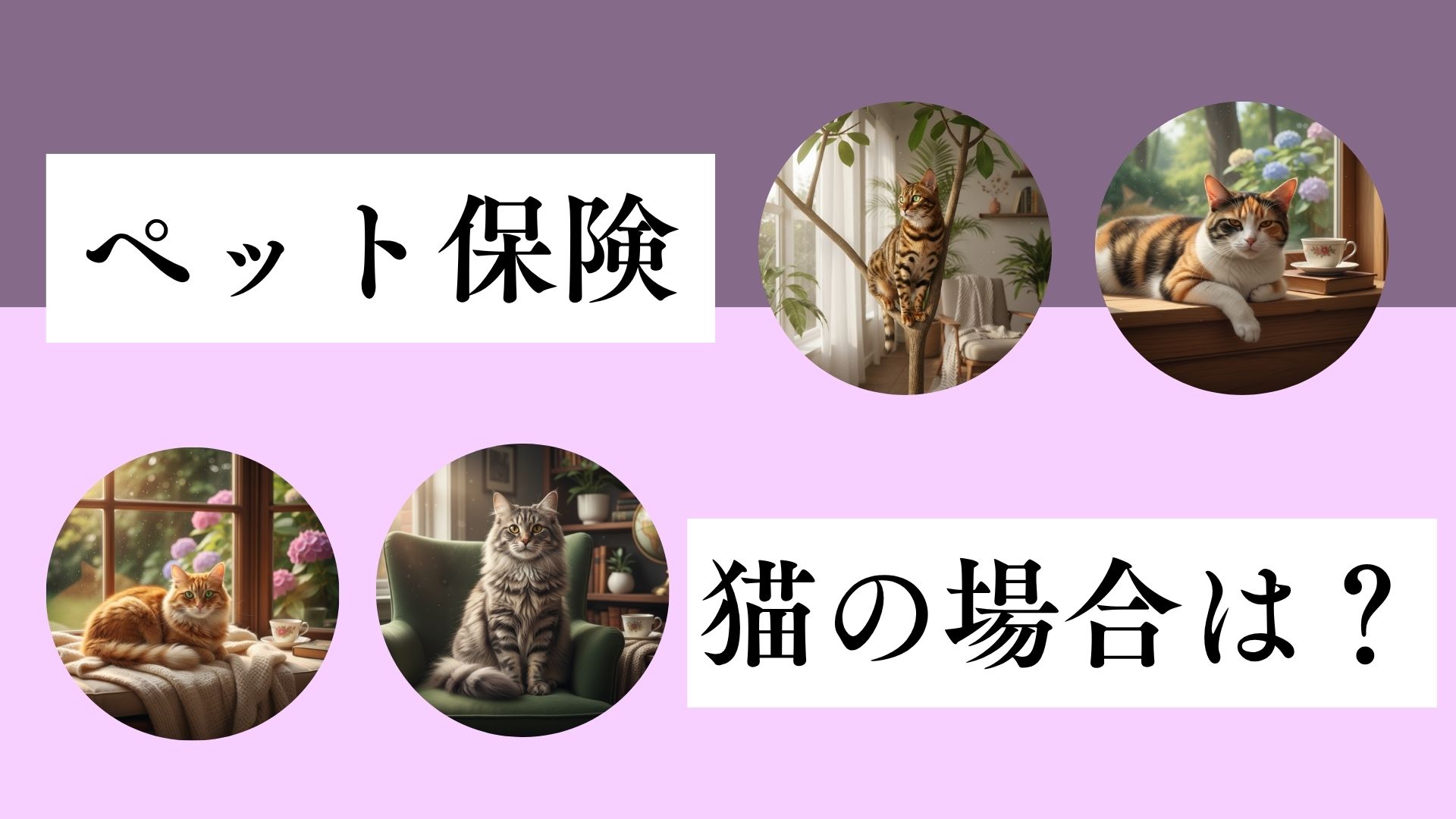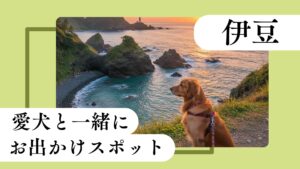愛猫の“もしも”の医療費、あなたはしっかり備えていますか?
「猫は丈夫だから保険は必要ない?」「保険料が高くて継続が大変」「実はやめて後悔した…」
そんな本音や体験談も多い中で、猫のペット保険選びはとても悩ましいテーマです。
この記事では、実際の失敗談ややめた理由から見えてくる「猫の保険の本当の必要性」と、2025年最新の安い&使いやすい保険ランキング、プロが教える賢い選び方を徹底解説!
迷える飼い主さんが納得して選べるよう、丁寧&楽しくガイドします。
本当に猫にペット保険は必要?「いらない・やめた」理由を検証
「猫はあまり病気にならないし、保険って必要なの?」
「過去に入ってたけど結局やめてしまった…」
近年、猫のペット保険について「いらない・やめた」と感じる飼い主さんも増えています。
ここではそのリアルな理由や、本当に必要なのかを様々な角度から考えます。
「猫の保険はいらない」と考える主な理由と飼い主の本音
猫のペット保険に対して、「いらない」と考える飼い主さんは意外と多いもの。
その背景には保険料の負担感や、保険金を使う機会の少なさ、補償内容への不満など、現実的な悩みがあります。
愛猫家の本音をひもときつつ、なぜそう思うのか、どんなリスクがあるのか、率直に紹介します。
理由1:毎月の保険料が家計の負担になる(保険料が高い)
保険に加入していても、毎月の保険料が意外と高いと感じる飼い主さんが多いのが現実です。
特に猫は体が小さく、「大きなケガや手術が必要になることが少ない」と思われがち。
加えて年齢が上がると保険料が一気に上がるため、「ずっと払い続けるのは大変…」と感じて解約を考える人も少なくありません。
さらに多頭飼いの場合、家計へのインパクトはさらに大きくなり、保険料を節約したいと思う気持ちが強くなるのも納得です。
理由2:保険金を請求する機会が少なく、掛け捨てが「もったいない」
「実際、1年加入しても一度も保険金を使わなかった」
猫は犬に比べて通院回数が少ない傾向にあり、保険金請求のチャンスが少ないという声が目立ちます。
2024年のアイペット損保データによると、加入後1年以内に保険金を請求したケースは約60%。
裏を返せば、約40%の人は1年で1度も使わなかったということ。
「ずっと掛け捨てで終わるなら、貯金のほうが得なのでは?」と悩む気持ちもよく分かります。
理由3:補償範囲が狭く、使いたい治療が対象外だった
「せっかく保険に入ったのに、希望する治療が補償対象外だった…」
これもよくあるガッカリパターンです。
たとえば猫の多い「慢性腎臓病」や「歯周病治療」など、補償範囲外の病気や治療が思ったより多いと、「意味がなかった」と感じることも。
また、先天性疾患や予防接種など、保険の免責事項をきちんと確認せずに加入し、いざという時に使えなかったという後悔も聞かれます。
選ぶ前に補償内容・対象外治療を必ずチェックすることが重要です。
ペット保険を「やめた」飼い主の後悔と失敗談
「保険なんていらない」と感じて解約したものの、後で「やめなきゃよかった…」と後悔する飼い主さんも多いもの。
リアルな体験談をもとに、やめた後に訪れた予想外の出費やトラブルを紹介しつつ、猫の保険選びで失敗しないためのヒントをお伝えします。
解約後に高額な治療費が発生して後悔
「保険料がもったいない」と思ってやめた直後、突然の大きな病気やケガで高額な医療費が発生し、「あのまま続けていれば…」と悔やむケースが少なくありません。
たとえば慢性腎臓病の場合、1年間で平均27万円以上の治療費が必要(※参考:アニコム 家庭どうぶつ白書2023)。
いったん発症すると長期治療になりやすく、家計に重くのしかかることも。
「予想外の出費が怖い…」と感じるなら、やめずに続けておくほうが安心できるかもしれません。
高齢になってからの再加入の難しさ
「若いうちは大丈夫」と保険を解約しても、シニア期に入ってから再加入しようとしたら加入条件が厳しくなっていたという声も多いです。
多くのペット保険は加入できる年齢に上限があり、7~12歳以降は新規加入できなかったり、持病があると入れないケースも。
特に高齢になればなるほど保険料も高くなるため、「もっと早く続けていればよかった…」という後悔につながることも少なくありません。
猫の平均的な治療費とペット保険の必要性
「やっぱり猫の保険っていらない?」と迷う飼い主さんも多いですが、猫も若い時から病気やケガのリスクが高いことが分かっています。
アイペット損保の調査では、加入1年以内に約60%が保険金を請求しており、実は「思っていたより発症リスクが高い」のが現実です。
特に入院・手術になると、治療費は数十万円単位でかかることも。
慢性腎臓病の年間治療費は平均27万円以上、他にも交通事故や誤飲・異物除去手術など、一度の治療費が10万円~30万円を超えることも珍しくありません。
猫の医療費は「いざという時に急に大きな金額が必要になる」ため、安心と経済的リスク分散のために保険は有力な選択肢だといえるでしょう。
猫のペット保険 失敗しない選び方【安さ・補償・使いやすさ】
「いざ入ってみたら後悔した…」
そんな失敗を避けるためには、安さ・補償内容・使いやすさという3つの視点から猫のペット保険を選ぶのが大切です。
ここでは、それぞれのポイントを具体的なチェック項目とともに解説。
愛猫のために、本当に納得できる「後悔しない保険選び」を一緒に考えていきましょう!
ポイント1:保険料を抑える「安い」プランの選び方
猫の保険選びで最も気になるのが保険料の安さ。
保険料を少しでも抑えるためには、「補償割合」「免責金額」「補償対象の範囲」「プランの絞り込み」がポイントです。
たとえば補償割合は70%・50%から選べる商品が多く、70%は自己負担が少なくなる一方、保険料は高めに。
一方、50%にすると保険料がぐっと安くなりますが、自己負担額が増えるため、毎月の家計や「いざという時にどこまで補償を求めるか」を天秤にかけて選びましょう。
また、免責金額(一定額までは自己負担)が設定されていると、保険料は安くなりやすいですが、ちょっとした通院には使えないことも。
「通院補償が不要」と割り切れるなら、手術・入院特化のプランを選ぶことでさらに保険料を抑えることも可能です。
加えて、各社で補償内容や年間限度額、終身継続時の値上がり幅も異なりますので、「トータルで見て無理なく続けられる」商品を探してみましょう。
補償割合(50%・70%など)と免責金額のバランス
保険料と自己負担額は補償割合と免責金額の設定次第で大きく変わります。
例えばアイペット損保の「うちの子」シリーズは30%・50%・70%の3タイプから選べ、補償割合が上がるほど月額保険料も高くなります。
一方、免責金額があるプラン(例:うちの子ライトの手術補償は3万円未満は対象外)だと、月々の保険料が安く抑えられますが、ちょっとした通院や軽症は実費負担になります。
「どこまで補償してほしいか」「毎月の予算は?」をしっかりイメージし、家計に無理なく続けられるベストバランスを見極めましょう。
通院補償なし(手術・入院特化)プランの検討
「とにかく保険料を抑えたい」「大きなケガや手術の備えだけでいい」
そんな場合は、通院補償なしで手術・入院に特化したプランも有力な選択肢です。
たとえば「うちの子ライト」や「スーパーペット保険」などは手術費用や連続入院に限定して90%など高い補償割合を提供。
日常的な通院や軽い症状は自己負担ですが、高額治療費のリスクを大幅に減らせるのが魅力です。
健康なうちは出費を抑え、万一の大きな出費をガードしたい方は、ぜひこうしたプランもチェックしましょう。
終身の保険料の値上がりカーブを確認
意外と見落とされがちなのが「保険料の値上がり幅」。
多くのペット保険は年齢ごとに保険料がステップアップし、7歳・9歳・12歳などシニア期に急に高くなるケースも。
長く続けるつもりなら「どこまで値上がりするか」をシミュレーションし、「トータルの負担」が無理のない範囲か確認しましょう。
中には保険料の上がり方がなだらかで、「値上げストップ年齢」を設けている商品もあります。
こうした点も比較材料にすると、後悔しにくい保険選びができます。
ポイント2:猫特有の病気に備える補償内容
保険料だけで選ぶと、猫特有の病気やトラブルが補償対象外だった…という失敗も。
とくに注意したいのは「慢性腎臓病」「尿路結石」「歯周病」「異物誤飲」など、猫がかかりやすい疾患です。
近年のペット保険は「歯科治療もカバー」「異物誤飲OK」など補償範囲を広げる商品も増えていますが、すべての保険が対象ではありません。
「補償範囲にこれらの病気が含まれるか?」を必ずチェックし、公式サイトや重要事項説明書で細かく比較しましょう。
また、慢性疾患への通院や長期治療に強い保険、特定の疾患に手厚い商品など、愛猫の体質やライフステージに合わせて選ぶのも賢いコツです。
慢性腎臓病など、猫がかかりやすい病気のカバー範囲
慢性腎臓病は猫の死亡原因でも最も多い疾患であり、長期の通院・治療が必要になることも。
一頭あたりの年間治療費は平均27万円以上と、家計へのインパクトは絶大です。
この病気を補償対象に含めているかどうかは各社で差があるため、「慢性腎臓病・腎不全」の補償の有無は必ず確認しましょう。
また、異物誤飲や尿路結石、糖尿病、心疾患なども含めてカバーできる保険は、長期的な安心材料となります。
歯科治療(歯周病など)の補償の有無
猫の高齢化とともに増えているのが「歯周病」「口内炎」「抜歯」などの歯科疾患。
これらは保険会社によっては補償対象外となっていることも少なくありません。
愛猫の健康寿命を考えるなら、「歯科治療の補償あり」の保険を選ぶのがおすすめ。
とくに歯周病の治療費や、全身麻酔が必要な場合は高額になることもあるため、見積り時に歯科の補償範囲も細かく比較しましょう。
ポイント3:利便性の高い利用しやすい保険を選ぶ
どんなに保険料や補償が良くても、「使いにくい」「請求が面倒」では意味がありません。
保険証を提示するだけで自己負担だけ支払う「窓口精算」、Webやアプリでサクッと請求できる仕組み、24時間の獣医師相談サービスなど、「使いやすさ」も保険選びの大切なポイントです。
特に通院・入院が続く場合や、初めての保険加入の場合は「いざという時にすぐ使えるか?」を意識して選びましょう。
窓口精算(保険証提示)の対応状況と対応病院数
アイペット損保やアニコム損保のように、全国6,000以上の動物病院で窓口精算ができる保険はとても便利です。
保険証を提示するだけでその場で保険が適用され、自己負担分のみの支払いでOK。
「急な高額治療費が怖い」「請求手続きが苦手」な方は、窓口精算付きのプランが断然おすすめ。
一方で、かかりつけ病院が対応外の場合や、地域によっては未対応の場合もあるため、事前に公式サイトで提携病院検索を活用しましょう。
Web・アプリでの保険金請求手続きの容易さ
請求手続きがWebやアプリで完結できるかどうかも使いやすさの大きな違い。
「紙の書類を郵送しなければいけない」「領収書を添付するのが手間」といった煩雑さがあると、つい後回しにしがちです。
スマホで写真を撮ってアップロードするだけ、マイページで簡単入力できるサービスなら、忙しい飼い主さんでもラクラク請求が可能。
事前に「請求の流れ」「使えるデジタルツール」も必ずチェックしておきましょう。
保険料が「安い」猫のペット保険おすすめランキングTOP5
「毎月の負担が少ない保険を選びたい」「できるだけお得に安心を手に入れたい」――そんな方におすすめなのが、保険料が安い猫のペット保険ランキングです。
ここでは、2025年最新の各社プランの中から「家計にやさしいのに、しっかり安心」なコスパ抜群の5商品を厳選。
それぞれの特徴や安さの理由、どんな人に向いているかを徹底解説します。
「安いだけじゃない“納得の理由”」に注目しながら、愛猫の保険選びの参考にしてください。
1位:リトルファミリー少額短期保険「にゃんデイズ」
業界最安クラスの保険料で注目されているのが、「にゃんデイズ」。
補償は通院・入院・手術をカバーしつつ、免責金額なし&シンプルなプラン設計で、0歳加入時の月額保険料は最安水準。
とにかく「毎月の保険料を極力抑えたい」「健康なうちに早く加入したい」方にぴったり。
長期的な保険料の上がり幅も比較的ゆるやかで、継続もしやすい点が魅力です。
ただし補償条件や対象年齢、プランごとの細かな違いもあるので、公式サイトで最新情報を必ずチェックしましょう。
業界最安クラスの保険料を実現(検証条件:〇歳・猫種)
リトルファミリー少額短期保険「にゃんデイズ」は、0歳から加入できる最安級のプラン。
年齢や猫種ごとに保険料が設定されており、子猫のうちから加入すると、保険料の合計負担が圧倒的に少ないのが特徴です。
「医療費リスクを低コストで備えたい」「まずはお試しで入ってみたい」人には特におすすめ。
また、シンプルな契約内容で、請求手続きも比較的簡単なのも選ばれている理由です。
2位:SBIペット少額短期保険「うちのペット」
続いて「安さ×バランス」で人気なのが、SBIペット少額短期保険の「うちのペット」。
保険料が安いだけでなく、補償範囲も必要十分で、入院・手術はもちろん、通院もカバーするプランもあり。
必要な補償だけ選んでカスタマイズできるので、「家計と相談しながら内容を調整したい」「保険料と補償のバランスを重視したい」人にも最適です。
免責金額や日額制限などの条件もしっかり確認したうえで、納得のいく形で選びやすいのが強みです。
保険料と補償内容のバランスが良い低価格帯プラン
SBIペット少額短期保険「うちのペット」は、「安さ+必要な補償だけ」というカスタマイズ性が特長。
プラン選びの柔軟性が高いので、「とりあえず最低限の補償だけ」「でも大きな出費には備えたい」という幅広いニーズに応えられます。
保険料シミュレーションも分かりやすく、年齢や条件ごとに比較して選べるのも嬉しいポイントです。
3位:ペットメディカルサポート「PS保険」
「長く続けるなら、保険料の上がり幅も大事にしたい」――そんな方に人気なのが、ペットメディカルサポートの「PS保険」。
3年ごとに保険料が見直される仕組みで、値上がり幅が緩やかなため、シニア期も無理なく継続しやすいと評判。
補償も通院・入院・手術すべてに対応し、安さと安心のバランスを両立したい方には有力候補です。
特に中長期でのコスパや、「解約したくない」「ずっと安心して続けたい」ニーズに向いています。
3年ごとの保険料見直しで値上がり幅が緩やか
PS保険の最大の特徴は、年齢ごとの急な値上がりがない点です。
3年ごとに段階的に保険料が見直される仕組みのため、「急に月額が跳ね上がって払えなくなった…」という心配がありません。
初めて保険に入る方、家計の長期プランを立てている方におすすめの安心設計です。
4位:FPC「フリーペットほけん」
「生涯での保険料アップをできるだけ抑えたい」という方にはFPC「フリーペットほけん」もおすすめ。
値上がり回数が生涯で3回だけというめずらしい設計で、途中で「保険料が上がりすぎてやめたくなった…」を防げます。
また、通院・入院・手術のバランス型補償や、免責金額なし・保険金請求の手軽さも魅力です。
「将来も安心して長く続けたい」方にはうってつけです。
生涯の値上がり回数が少なく、長期で安心
FPC「フリーペットほけん」は、途中での大幅値上げリスクを回避したい方に人気。
生涯で3回しか保険料が上がらないため、トータルの負担額が見通しやすく、長い目で見て家計管理しやすいのが強みです。
また、オンラインで簡単に見積もり・申込ができる点も、多忙な飼い主さんに選ばれています。
5位:au損保「ペットの保険」(通院・入院・手術プラン)
「大手キャリアで安心したい」「キャリア決済やポイント払いも活用したい」方にはau損保「ペットの保険」もおすすめ。
auユーザー以外も加入でき、通院・入院・手術までカバーする総合補償タイプで、保険料の安さと支払手段の多様性が強み。
特に「キャリア決済でラクラク支払いしたい」「au PAYを活用したい」という人は注目すべき一社です。
auユーザー以外も加入可能、キャリア決済も選べる
au損保「ペットの保険」は、au利用者限定ではなく誰でも申込み可能。
クレジットカードはもちろん、コンビニ払いやau PAY決済にも対応し、支払いの選択肢が豊富。
「ネットで手続き完結」「最小限の負担で必要な安心をゲット」したい方にはおすすめです。
補償内容で選ぶ!人気の猫のペット保険主要10社比較
「とにかく安さ重視」だけではなく、「補償内容を重視したい!」という方も多いはず。
ここでは、人気のペット保険主要10社の中から、補償範囲や特徴ごとに比較。
愛猫のライフスタイルやご家庭のニーズに合わせて、あなたにぴったりのプランを見つけましょう!
全疾病・ケガ対応の総合型プランから、高額医療に特化したプランまで網羅的に紹介します。
全疾病・ケガ対応の総合補償プラン
「通院・入院・手術のすべてを補償してほしい」「猫の慢性疾患や突発的なケガにも幅広く備えたい」という方には、総合補償プランがおすすめです。
代表的な商品には、アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」やアイペット損保「うちの子」などがあり、どちらも全国6000以上の動物病院で窓口精算が利用可能。
補償割合も50~70%などから選べて、病気の早期発見・治療や長期療養にも強みがあります。
ペットの一生をトータルでサポートしたい方に安心の選択肢です。
アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」
窓口精算の利便性・対応病院数No.1が魅力の総合補償型ペット保険。
通院・入院・手術のすべてをカバーし、多頭割引や健康割増引も充実。
万一の高額治療から、慢性疾患の通院まで幅広く備えたい方にピッタリです。
補償割合や年間限度額もわかりやすい設定なので、迷ったらまず候補にしたい1社です。
アイペット損保「うちの子」
3つの補償プラン(30%・50%・70%)から選べる柔軟さと、通院・入院・手術すべてを手厚くカバーする安心設計。
犬・猫ともに人気が高く、「窓口精算の簡単さ」「終身までのサポート」「細やかな補償設計」が評価されています。
年齢や体重、猫種ごとに保険料が算出されるので、まずは見積もりでシミュレーションしてみましょう。
入院・手術に特化した高額医療向けプラン
「大きな手術や高額医療費のリスクだけは絶対にカバーしたい」
そんな方には、入院・手術特化型のプランが有力候補!
こちらは通院補償を省くことで、保険料を抑えつつも一回の治療費が高額になりやすい猫の入院・手術に重点を置いています。
代表例はアニコム損保「どうぶつ健保ぷち」や、アイペット損保「うちの子ライト」など。
「普段は健康だけど、万一の大きな出費に備えたい」方や、家計重視の方におすすめです。
アニコム損保「どうぶつ健保ぷち」
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」よりも割安な保険料で、入院・手術に絞ったシンプル設計。
万一の大きな出費にしっかり備えたい人や、「通院は自費で大丈夫!」と割り切る方にぴったり。
アイペット損保「うちの子ライト」
通院補償を省いて保険料をグッと抑えつつ、手術費用を最大90%補償する高額医療特化型プラン。
加入年齢の上限がなく、長期的に大きな出費だけガードしたい人にはピッタリです。
高額な治療費への備えを最優先したい人はぜひ比較してみましょう。
猫の保険加入で気になる疑問Q&A
「実際に入る前にここだけは知っておきたい!」「保険選びの“最後のひと押し”が欲しい」
そんな飼い主さんの疑問にズバリお答えするQ&Aコーナーです。
細かい条件や不安なポイントまでしっかり解説するので、疑問をクリアにして納得の保険選びをしましょう。
Q. 待機期間とは?加入後すぐに保険は使える?
多くの猫のペット保険には「待機期間」が設けられています。
これは加入後すぐは補償が始まらず、一定期間(例えば30日など)を経てから保険金の請求が可能になる制度。
理由は、すでに発症していた病気やケガでの駆け込み加入・モラルリスクを防ぐためです。
保険会社ごとに待機期間や補償対象となる条件が異なるため、「加入したその日から保険が使えるわけではない」と認識しておきましょう。
急な治療費が心配な場合は、元気なうちから早めに準備しておくのが安心です。
Q. 猫の年齢がわからない保護猫でも加入できる?
近年では年齢不詳の保護猫もペット保険に加入できるケースが増えています。
通常、血統書やワクチン証明書などで年齢を確認しますが、ない場合は動物病院での健康診断や獣医師による「推定年齢」で申込OKな保険も多いです。
保護猫の場合は「お迎え日を誕生日として登録」できる保険会社もあるので、まずは事前に相談・確認しましょう。
Q. 健康診断の費用や予防接種は補償対象外?
猫のペット保険は「発生した傷病の治療費」が補償対象であり、健康診断やワクチン接種・予防目的の医療費はほぼ補償外となっています。
また、避妊・去勢手術やノミダニ予防薬、定期健診なども免責事由となるのが一般的です。
一方で、診断のための検査費や必要に応じた追加検査・治療は補償の対象になることも多いので、商品ごとの詳細をしっかり確認しましょう。
Q. 猫のペット保険は終身で契約できる?
ほとんどの猫のペット保険は一度加入すれば終身まで継続可能です。
ただし「新規加入できる年齢」に上限があることが多く、たとえば7歳11か月・9歳11か月・12歳11か月までなど各社で異なります。
年齢制限を過ぎると「どんなに健康でも加入できない」ため、元気なうちから早めに検討・加入するのが大切です。
なお、解約しない限りは年齢を重ねても補償が続くので、シニア期も安心して使えます。
まとめ:愛猫のライフステージと家計に合った最適な保険を見つけよう
ここまで猫のペット保険のリアルな「いらない・やめた」理由から、失敗しない選び方、最新の安い&おすすめ保険ランキング、補償内容や疑問解説まで一気に解説してきました。
結論、猫も予想以上にケガや病気のリスクが高く、特に高額医療や慢性腎臓病などの長期治療では家計に大きな負担がかかるケースも少なくありません。
だからこそ、保険料・補償内容・使いやすさをバランス良く比較し、ご自身や愛猫のライフスタイル、そして将来を見据えた最適な保険選びがとても大切です。
「どこまでの補償が必要?」「いくらまでなら続けられる?」――迷ったときは、まず複数の保険で見積もり&シミュレーションをしっかり行い、納得いくまで比較検討しましょう。
「もしもの安心」は、ペットも家族もずっと笑顔で暮らせるための大切な備え。
ぜひ今回の記事を参考に、愛猫の一生に寄り添う“納得の保険選び”をしてください!